忘れられた戦後思想のツケが大学改革に影響している?
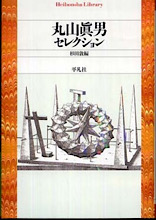 今回は丸山眞男の「軍国支配者の精神形態」(1949年)と「超国家主義の論理と心理」(1946年)について書こうと思っているのですが、
今回は丸山眞男の「軍国支配者の精神形態」(1949年)と「超国家主義の論理と心理」(1946年)について書こうと思っているのですが、
キッカケは思想とは直接関係のない本を読んだことでした。
(どちらの論考も『丸山眞男セレクション』(平凡社ライブラリー)に所収)
丸山などの戦後思想は僕が物心ついたときにはほとんど読まれていなかったと思います。
プルデューに言及したりして左翼を自認する大学教授が、ろくに丸山を読んでいなかったことに驚いたこともあります。
ポストモダニズムは欧米では自己批判の思想ですが、日本では自己批判的な意味を持つ戦後思想を過去へと追いやり、
バブル景気を背景に日本を肯定する役割を果たしました。
しかし、戦後思想は役割を終えたわけではなく、現在も解決されない問題として残り続けています。
それが最近出版されたある本に示されていました。
大学受験制度が来年から共通テストという新方式に変更されるにあたり、
英語の民間試験導入や国語の記述式回答などで文部科学省への批判が相次いだのは、記憶に新しいところです。
 そんなこともあって、佐藤郁哉の『大学改革の迷走』(ちくま新書:2019年)を読んでみたのですが、
そんなこともあって、佐藤郁哉の『大学改革の迷走』(ちくま新書:2019年)を読んでみたのですが、
意外にもその中で丸山眞男の「無責任の体系」が出てきたのです。
せっかくなので少々回り道をして、佐藤の本についても少々触れておきます。
佐藤は文科省などが主導する大学改革が、なぜ迷走しているのかを考察しています。
最初に、大学の履修登録の資料となる「シラバス」が、手本であったはずのアメリカのsyllabusと全然違うということを取り上げます。
電話帳のようなシラバスや、桐の箱に入れられたシラバスなど、アメリカ人が見たら目を見張ることでしょう。
そのような事態になってしまったのは、文科相やその諮問機関である中央教育審議会からの「御意向」を、
大学側が「忖度」した結果だと、佐藤は指摘します。
こうしてみると、日本の大学は、文科省が改革度を測るモノサシとして設定してきた各種の基準などを元にしてシラバスの理想形について「忖度」しながら、教員たちのシラバス作成やその監視・修正の作業を進めてきた、ということが言えそうです。(佐藤郁哉『大学改革の迷走』)
次に佐藤は、もともと工場の品質管理に用いられていたPDCAサイクルという言葉が、
大学改革関連の文章の中で使われるようになったことについて検証します。
工場で作られる製品に適用される方法が、どうして教育機関に持ち込まれたのか不思議になりますが、
どうやら文科省がビジネスの世界を参考にして大学改革を進めようとしたことに原因があったようなのです。
ここで佐藤は、早稲田大学ビジネススクール教授の山田英夫の「フレームワーク病」という言葉を紹介しています。
山田氏は、日本というのは、新奇なビジネス用語やフレームワークが次から次へと海外(主に米国)から輸入されて流行してきた「不思議な国」であるとします。また、日本のビジネスパーソン(特に若い人々)には、その流行に乗らないと取り残された気分になってしまったり、単に用語を使うことで分かったような気になってしまったりする傾向があるとし、それを「フレームワーク病」と呼んでいます。(『大学改革の迷走』)
この「フレームワーク病」に思い当たらない日本人は少ないと思います。
海外から形式だけを輸入してその内実に関心を払わないために、実質的な効果がなくなってしまうのが「フレームワーク病」です。
こうして内実のない形式だけが大流行します。
海外の影響を形式上にとどめて、自己都合の「翻案」をするのが日本人の特徴でもあります。
日本における大学改革の不幸は、政府あるいは内閣府や文科省などの府省が、外来のモデル(と一見そのように見えるもの)を付け焼き刃的に借用した上で大学現場に対して押しつけてきた、というところにあります。(『大学改革の迷走』)
海外のモデルを一次的権威として、国内の政府や府省が二次的権威となって、より下方へと権力的な振る舞いをする、
これを僕は広い意味での天皇制メカニズムだと考えているのですが、この権威主義的メカニズムについてはあとで取り上げます。
佐藤は、文科省や中教審などが、PDCAをきちんと理解せずに大学に押しつけたことと、
大学側が民間経営手法の「劣化コピー」に従うか従うフリをしたことを批判します。
ここには僕が〈内実に対するニヒリズム〉と名付けた日本人の表層執着志向が見られます。